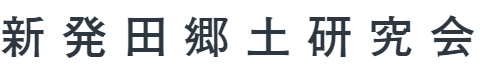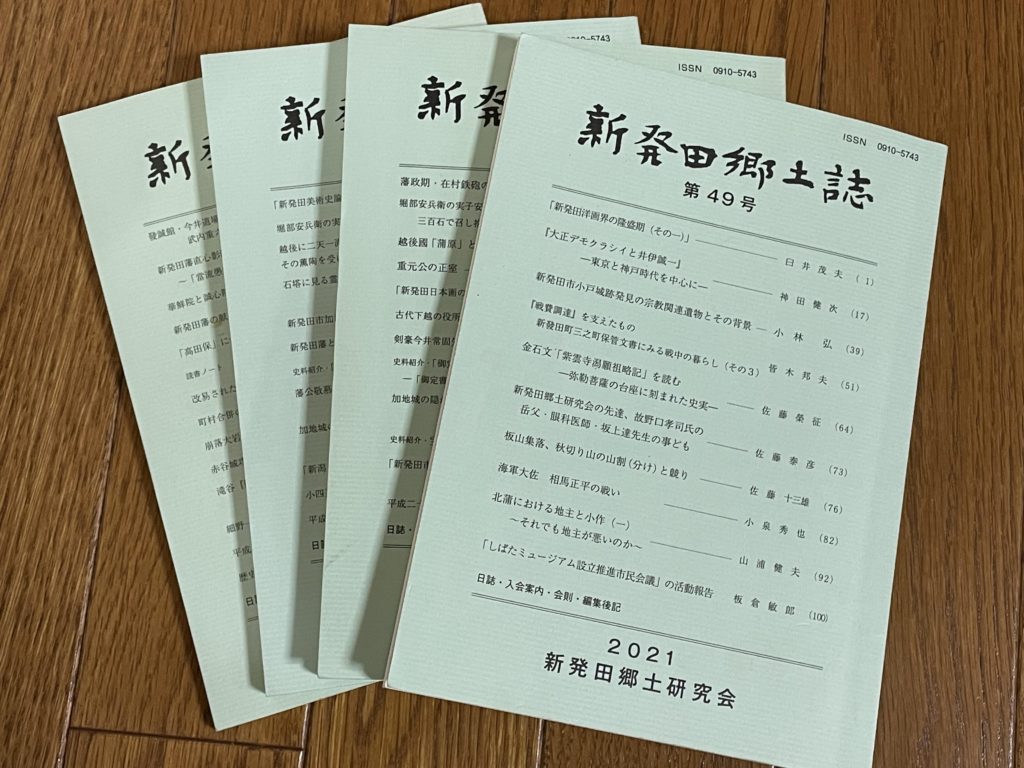
「新発田郷土誌」は会員の調査研究の発表や会の活動を記録した会誌で、とても価値あるものです。昭和37年(1962)に第1号が発行され、令和4年(2022)で50号となります。発行された会誌には興味深い論文が多数あります。本会の50周年を記念して、広く世の中に寄与するために総目次を公開します。内容に興味を持たれた場合は、新発田市立歴史図書館、新潟県立図書館、国立国会図書館で閲覧が可能です。バックナンバーの在庫が若干事務局にあります。 お求めになりたい場合は、「新発田郷土誌」バックナンバーの販売をご覧ください。
※国立国会図書館では、1~4号、24号の蔵書はありません。
※各図書館には、資料複写郵送サービスがあります。詳細は各図書館にお尋ね下さい。
※Windows検索機能でキーワードの検索ができます。
「Cntl」と「F」を同時に押す。現れる検索窓にキーワードを入力して「Enter」押すと、総目次内に存在するキーワードがオレンジ色、黄色で表示され、その場所にジャンプします。
第 1~10号
■ 第1号 昭和37年(1962)3月30日発行
新発田市史編さん委員会規程
市史編さんについての希望 新発田市長 原常一郎
市史編さんの進め方
―一般のご協力を―市史編さん委員長 波多野伝八郎
近世初期新発田藩の財政と払米 小村弌
古碑研究 杉原豊
石井銀太氏(島屋薬店)留書帳から抜書 波多野伝八郎
山草苅り物語 佐久間惇一
徒遊譚 ―世臣譜分註― 野口孝司
随筆 私の温故はし書 鬼木包次郎
附・郷土の石器、土器についてや、『ツベタの丘』のことなど
(資料調査)
一 上石川の獅子踊り 佐久間惇一
二 地区聞書 全委員
菅谷地区聞書 米倉地区聞書 川東地区聞書
五十公野地区聞書 赤谷地区聞書
「焼峰」地名考
(特別寄稿)
〝ナデ〟談義 大橋順二
市史編さん委員会日誌
巻末 新発田市史資料 蒐集古文書目録
■ 第2号 昭和38年(1963)3月10日発行
〔口絵〕・五十公野長坂遺跡全景 ・馬見坂出土の土師器、甑
・上車野発見の石斧類 ・上三光出土の剥片石器類
・下中山発見と伝えられる土偶 ・十二林出土の注口土器
・南俣開墾地発見のナイフ形石器
市史編さんに寄せて 新発田市長 大沼鐵男
一般市民のお力にご協力を―
新発田市内における考古学的調査
立教大学調査団 中川成夫 岡本勇 加藤晋平
新潟県新発田市の民家 東大工学部大学院 宮沢智士
新発田市の城館址(一) 伊藤正一
新発田藩の社倉についての若干の資料 松田時次
新発田川水系の水車について 竹内常治
新発田行 桑山与市
十返舎一九と新発田 杉原豊
―諸国道中金の草鞋から―
新発田市獅子舞・神楽調査資料 佐久間惇一
新発田藩史料(奉先堂文庫) 市立図書館古文書調査部
―御在城・御留守日記類 抄出目次―
新発田藩史料 豊田神社文書目録
〔今は昔〕・仙台藩お礼の石 (波)=波多野伝八郎
・与茂七の処刑 (N)=野口孝司
・映画『新しい土』と加治川の桜花 (波)=波多野伝八郎
・明治の新聞 『東北日報』から (N)=野口孝司
新発田市史編さん委員会日誌(抄)
■ 第3号 昭和39年(1964)2月20日発行
新発田藩(溝口氏)略年系譜
藩臣石原寛信について 藤井重雄
新発田藩の財政問題 小林弘
下寺内の弥生式文化遺跡 田中正治
郷土玩具聞書 川口栄三
「加治川治水工事の資料から」
岡田瀬替工事について 松田時次
滝谷村物産書出帳 波多野伝八郎
新発田市の城館址(二) 伊藤正一
資料から見た明治初年の新発田郵便小史 佐藤泰彦
執筆者紹介
(資料調査) 市内古文書あれこれ 杉原豊
(雑報一) 新発田市史(資料編)稿本成る
新発田市史資料 古文書目録(承前)
(推薦図書) 「二王子山麓民俗誌」 佐久間惇一著
〔今は昔)・清水園と県宗智 (波)=波多野伝八郎
・帰農武士の感懐 (波)=波多野伝八郎
新発田市史編さん委員会日誌(抄)(雑報二)
新発田市内の和算―とくに算学―について(一)理学博士 道脇義正
■ 第4号 昭和41年(1966)1月20日発行
〔口絵〕・加治要害山の初雪・宝光禅寺記・壺形土器・天正の古鐘
溝口氏における近世大名成立史序説 小村弌
阿賀北地方における考古学の現状と諸問題 関雅之
「つきあい」と村落構成
―新潟県新発田市茗荷谷部落の場合― 河上一雄
米倉村(現新発田市)の紙漉と削り花について 大竹義夫
近世後期新発田藩の穀留政策と米穀市場構造 永井洋一
民謡資料 ―赤谷を主として― 小柴清治・佐久間惇一
新発田市の城館址(三) 伊藤正一
〔余録〕・天正の古鐘・新撰伊呂波たとえ・安兵衛と学天
新発田市史刊行だより
・宝光寺世代譜 ・宝光寺鐘銘 ・広沢山宝光禅寺記
宝光寺雑考 波多野伝八郎
新発田市史古文書目録(承前)
藤戸神社奉額解説 理学博士 道脇義正
■ 第5号 昭和41年(1966)7月31日発行
(民俗特集号)
郷土史と現代(講演筆記) 文学博士 和歌森太郎
民俗資料の記録と整理 文学博士 直江広治
諏訪方御祭礼留書(抄)(職人町文書)
職人町雑記 杉原豊
上方参り道中附 高沢次郎七遺稿
新発田市飯島の昔話 高橋克章
藤戸明神由来(黒岩家文書)
■ 第6号 昭和47年(1972)2月25日発行
新発田城下町の成立 小村弌
資料 明治初年の新発田町の職業構成 市史近世部会
加治川及び坂井川流域の考古学的調査 関雅之
七里恭斎先生行状記 野口孝司
明治三十七年当時の新発田町市場 松田時次
新田について 竹内常治
資料 紫雲寺潟御新田由来記 (築井家文書)
油しぼりあれこれ 藤間登
謎の人物二題 僧于麟と圓明尼 波多野伝八郎
越後国蒲原郡石喜新村差出帳
(立教大学日本史研究室蔵)
新発田町における流木流通 関川直
新発田祭りの由来(抄) 故斎藤恭平
執筆者紹介
〔今は昔〕
・旧城下町新発田町考(その一)・(その二)・(その三)・(その四)
・越後新発田方言 (かわぐち生)=川口栄三
■ 第7号 昭和49年(1974)3月10日発行
新発田藩における郷村支配制度の確立過程 小村 弌
渟足柵の史的性格など ―越佐古代史メモ― 桑原正史
調査報告 池之端の居館址に関する地名の復元中世部会
新発田藩治水開発の周囲 波多野伝八郎
新発田藩における村万雑の一考察 込山二三男
近世の米倉村(中間報告) 斎藤寿一郎・真水 淳
調査報告 斎藤七郎家文書から収録した
年貢関係文書 永井洋一
明治初年における街道沿い村落の諸営業
―米倉地区調査メモ― 中山清
日清戦争前後の新発田第百拾六国立銀行
―『実際考課状』の若干の検討― 伊藤武夫
旧宝光寺墓地より出土の棺蓋書について 藤間登
執筆者紹介
農村の奉公人
―『新発田市史資料第五巻民俗』補遺― 佐久間惇一
資料 訴訟文・大正九年大字一同申合書大字板 佐久間惇一
資料 新潟県史資料から 松田時次
紹介 六石・佐藤寛先生 高橋礼弥
郷土山麓そぞろ歩き 竹内常治
〔余録〕・制札村法 (N)=野口孝司
・結婚につき籍を送る古い様式 (N)=野口孝司
・旧藩と茶 (波)=波多野伝八郎
・戊辰役資料
・旧新発田本村町名調
■ 第8号 昭和50年(1975)3月10日発行
近世の中妻村と高沢家 伊藤充
地租改正と農業生産力の地域性について 中山清
新発田町における明治三十四年町村合併 中村義隆
大正末期米倉村の村民所得 伊藤武夫
井上桐麿家―五十公野組大庄屋 斎藤正夫
御倹約年限中上げ物覚 波多野伝八郎
三日市藩調査概要・藩主系譜・三日市藩〔史料〕
石川よし子
三日市藩の藩領 坂輪恵子
旧新発田藩士の拓地記録 松田時次
執筆者紹介 波多野先生を悼みて 小村 弌
波多野伝八郎先生を悼みて 佐久間惇一
晩年の歌(一) 波多野伝八郎
波多野伝八郎略年譜 高橋礼弥
晩年の歌(二) 波多野伝八郎
杉原先生の憶い出 波多野伝八郎
杉原先生をしのぶ 赤城源三郎
遺詠を拾って
杉原豊の略歴と業績
〔今は昔〕
・新発田領内の種痘 (高橋)=高橋礼弥
・大正初期の新発田の野菜市場 (松田)=松田時次
・藩主の台輪見物 (高橋)=高橋礼弥
・新発田八景 (高橋)=高橋礼弥
■ 第9号 昭和51年(1976)6月30日発行
巻頭言 ―歴史に生気を与える人へ― 市史編纂委員長 野口孝司
古四王神社の分布 桑原正史
新発田城下の年中行事 武田広昭
維新期における村役人層の政治行動 真水 淳
―新発田藩領の明治三年村替反対運動―
大正後期における新発田の思想と文化
―社会主義思想の浸透に関連して― 五百川清
三日市藩の江戸夫役について 石川よし子
新発田藩に於ける藩学と異学と私学 斎藤正夫
「資料紹介」蒲原馬車会社の設立と経営 新井田玄道
執筆者紹介 溝口氏歴代の墓塔 小野田十九
新発田藩史料 時々申渡留帳 高橋礼弥
〔今は昔〕
・休み石 (高)=高橋礼弥
・蒲原馬車の話(一)・(二)
■ 第10号 昭和52年(1977)7月30日
五十志神社の成立
―御霊信仰と与茂七火事― 佐久間惇一
三日市藩と下関村渡辺三左衛門家 坂輪恵子
織豊期における大名の一類型
―与力大名溝口氏の存在形態― 安池尋幸
清涼院様一件
―新発田藩天明・寛政期の事件― 高橋礼弥
新発田藩に於ける藩学と異学と私学(二) 斎藤正夫
新発田の郭を語る 松田時次
「新発田新聞」から見た旧歩兵第十六連隊の一断面 熊倉弘基
「新発田方言番附」をめぐって 野口幸雄
市史古代・中世の項目と部会の活動経過 古代・中世部会
新発田市史〈近現代編〉の構想をめぐって 五百川清
新発田藩史料 慶応四年時々申渡留帳(二) 高橋礼弥
市史編さん委員会による編集発行を終るに当り 野口孝司
第11~20号
■ 第11号 昭和57年(1982)10月30日発行
〔口絵〕・村尻遺跡弥生時代出土品(ヒト形土器)
・木像十一面観音座像(大字下中 若宮八幡宮)
・諸法山菅谷寺(大正期)
・旧江戸参勤街道宿場(市内大字山内)
発刊のことば 新発田郷土研究会会長 野口孝司
「新発田郷土誌」の再刊を祝って 新発田市教育長 高橋恂三郎
お梅様のご婚礼 野口孝司
新発田市周辺の自然の記録 鶴巻精治
肥田野三代と困学塾 杉浦英午
しばたの「わらべ唄」 佐久間惇一
大野倹三郎小伝 ―新発田藩戊辰戦争悲話― 高橋礼弥
〝青い目をした人形〟余聞 川口栄三
新発田および周辺における和算家 鈴木康
地名 五十公野 斎藤正夫
新発田市の姓氏(名字) 福岡与一
菅谷不動尊 中倉貞一
樅の木を残して 能仲貫一
新発田の旧町名をたずねる 故波多野傳八郎
昭和五十六年度新発田市指定文化財
村尻遺跡出土品他 新発田市教育委員会
史跡探訪に参加して〔新発田市山内・赤谷〕 市井愛子
〔囲み記事〕
・諸事沿革抄 (佐久間)=佐久間惇一
・九代藩主直侯のよみかた (野口)=野口孝司
・文化財保護シンボルマーク
■ 第12号 昭和58年(1983)12月3日発行
〔口絵〕・新発田藩第十一代藩主溝口直溥侯着用の甲冑
・湯の平温泉図(大正末年頃)
幕末の藩医村山玄琢略伝 野口孝司
社会主義中尉と軍事史家
―松下芳男の二つの顔― 荻野正博
続 新発田のわらべ唄 佐久間惇一
新発田組大庄屋小川心斎家 斎藤正夫
あわびを食べない家 鈴木秋彦
―新発田藩重臣溝口伊織家の事例を中心として―
本多利明の出身地をめぐって 鈴木 康
松田観泉と〝蓮の露〟 川口栄三
新発田祭の台輪所感 高橋善夫
菅谷不動尊(二) 中倉貞一
社講宗之丞の寺を訪う 藤間登
上鉄炮町と周辺の今昔 佐藤秀一
史料 天保五・六年 御触書・申渡書 留帳 高橋礼弥
大倉喜八郎家の屋敷あと 能仲貫一
事業部会報告 ―五十公野周辺史跡めぐり― 事業部会
〔囲み記事〕
・新発田藩政当時の盆歌 (佐久間)=佐久間惇一
・当時流行の俗謡(二) (佐久間)=佐久間惇一
・諏訪と諏方 (野口)=野口孝司
・三角だるま (川口生)=川口栄三
■ 第13号 昭和57年(1984)10月25日発行
〔口絵〕・山本芳翠 「裸婦」
・正保四年家中屋敷図の部分図
阿賀北の人たちの移民史 松田時次
新潟県の郷土玩具 川口栄三
新保村・大友村境界問題訴訟 土田義男
桂病院応接間の「裸婦」 荻野正博
佐々木地区地名と地形の一考察 斎藤正夫
高橋光威と人力車夫・臼井鹿蔵 高橋明雄
黒川村持倉の狩猟 佐久間惇一
菅谷不動尊(三) 中倉貞一
大倉喜八郎翁の孝心 能仲貫一
佐々木全斎について 鈴木秋彦
―幕末の伯耆で活動した新発田出身の浪人医師―
史料 天保七・八年 御触書・申渡書 留帳 高橋礼弥
〔囲み記事〕
・新発田の洋学校と中学と高等科 (野口)=野口孝司
・山土産の玩具 (佐久間)=佐久間惇一
■ 第14号 昭和61年(1986)2月25日発行
〔口絵〕・菅谷寺庫裡(昭和初期)
・復興記念碑 ―野口家先祖の略歴を述べた碑―
・軍旗祭りに曳きだしの下町台輪(昭和十一年)
久米復仇史談に見るミステリ 阿達義雄
越後の織物 杉本耕一
白勢和一郎巴里通信
荻野正博「桂病院応接間の『裸婦』」訂正 荻野正博
大栗田の塩木仕事 佐久間惇一
参勤交代制度と新発田藩道中御行列
―「御下向之節所々江罷出候面々場所附」の紹介― 五十嵐喜一郎
諏訪祭礼と新発田台輪 高橋善夫
芭蕉の道から ―築地・新潟間の考察― 斎藤正夫
紫雲寺潟干拓と小栗美作 韮澤定吉
小見村禅宗旨人別改め帳 藤間登
外交官村長野口多内翁の蔵書 倉島和四蔵
大倉製絲新発田工場の創業 能仲貫一
菅谷不動尊(四) 中倉貞一
五十公野さん 鈴木康
新発田市における最近の発掘調査 新発田市教育委員会
史料 寛政元年 御触書・申渡書 留帳 高橋礼弥
新刊紹介 佐久間惇一著『狩猟の民俗』 鈴木秋彦
近刊案内 佐久間惇一著『新発田の昔話』 鈴木秋彦
事業部報告 ―三面集落探訪― 市井愛子
〔囲み記事〕・米沢への木流し (佐久間)=佐久間惇一
・新潟・新発田間乗合自動車の運行 (斎藤)=斎藤正夫
・新発田藩の律(刑法)(一) (高橋)=高橋礼弥
・新発田藩の律(刑法)(二) (高橋)=高橋礼弥
■ 第15号 昭和62年(1987)3月29日発行
〔口絵〕・奉先堂起御絵図
・下町 神明宮祭礼に曳き出しの金魚台輪
(大正十五年)
板倉行蔵覚書 ―久米孝子手続簿― 阿達義雄
山内きう女覚書(一)
―昔、父親様から聞いた話の覚え―
山内きよの筆録 荻野正博解説・注
湯沢町土樽地区の狩猟習俗(上) 佐久間惇一
昭和年代における治水・利水史の一端について(上)
松田時次
堀部家の後裔 五十嵐喜一郎
ある武士の経歴 ―野村信成伝― 藤間登
豊田荘と八幡信仰 斎藤正夫
小報告 新発田を訪れた良寛 高橋礼弥
諏訪神社と台輪祭礼に関する
新発田図志料抜粋解読による考察 高橋善夫
新発田藩主の宝光寺墓所を訪ねて
―歴代藩侯墓塔の位置― 佐藤秀一
人物紹介 大倉喜八郎翁 能仲貫一
井伊誠一文書のこと 荻野正博
一休神社 中村孝太郎
史料 寛政二年御触書
申渡書留帳(町奉行) 高橋礼弥 翻字
事業部報告 ―本成寺と中之島村
大竹与茂七関係遺跡めぐり― 福岡光二
―菅谷地区の史跡めぐり― 福岡光二
耕地整理と農業用水の整備における地理的考察
―新発田市松浦地区の事例― 千代智里
〔囲み記事〕・江ノ島弁財天と長堀検校のこと 渋谷文則
・『旧記抜書』より 佐久間惇
・誉田別尊と亀の受難(一)・(二) 加藤道夫
(新刊紹介)
・佐久間惇一他編著『関川郷の民俗』 鈴木秋彦
・宮 栄二編『雪国の宗教風土』 鈴木秋彦
・小林八郎再話 宇尾野林也版画『伝説大里峠』 佐久間惇一
・新潟日報事業社出版部
『新潟県人物群像Ⅰ―武』 鈴木秋彦
・鈴木 康編著『城下町しばた』 鈴木秋彦
(近刊案内)・『昔のしばたの暮らし』 川瀬勝一郎
■ 第16号 昭和63年(1988)2月25日発行
〔口絵〕・新発田城を描いた六曲一双屏風
・明治三四年 旧制県立新発田中学校練技会
(野球部)部員写真 ・同上 部員同志の激励文
供養の儀礼 ―造塔と遺物― 大沼淳
櫛形山脈中南部の山城(上) 木村尚志
新発田藩の藩札 鈴木正敏
全国的探索と隠遁的逃亡
―久米幸太郎敵討の盲点― 阿達義雄
湯沢町土樽の狩猟習俗(下) 佐久間惇一
新発田・新潟付近の交通路 桑原孝
山内きう女覚書(二) 山内きよの筆録 荻野正博解説・注
―昔、父親様から聞いた話の覚え―
新発田藩戦死者の墓碑 高橋礼弥
―明治戊辰戦争越後・庄内口戦い 余録―
大杉栄『自叙伝』の登場人物について 荻野正博・山口進
昭和年代における治水・利水史の一端について(下)松田時次
山岡鉄太郎の書 藤間登
『小説・大倉喜八郎』の連載にあたって 岡本巌
「五十公野」考 斎藤正夫
泉町台輪の製作 加藤道夫
―笠鉾台輪から生まれ変わった白木の台輪―
史料 寛政三年 御触書 高橋礼弥 翻字
・申渡留帳(一)(町奉行)
〈史跡探訪〉・村上市史跡等探訪 福岡光二
・諏訪峠石畳道、平等寺薬師堂探訪 福岡光二
〈小報告〉菅江真澄の「ひなのひとふし」 鈴木康
〔囲み記事〕
・「北越月令」抄(一)・(二)・(三) 佐久間惇一
・新発田藩士 西南の役参加出願書 松田時次
(新刊紹介)・山口 進著『新発田教育運動史』 荻野正博
(近刊案内)・佐久間惇一編
『波多野ヨスミ女昔話集』 鈴木秋彦
(近刊〈復刻本〉紹介)新発田市史編さん委員会編
『新発田市史資料編 新発田藩史料』 全三巻
■ 第17号 平成元年(1918)3月25日発行
〔口絵〕・巻 菱湖筆「職人町」額面纏(表面・裏面)
櫛形山脈中南部の山城(下) 木村尚志
〔口絵写真解説〕
巻 菱湖筆の「職人町」額面纏 鈴木秋彦
『芝田古今詩稿』とその周辺(上) 帆刈喜久男
堀部安兵衛武庸覚書(上) 高橋礼弥
武士のフィナーレ 遠藤利信
―堀部安兵衛の最期を追って―
シバタ氏と溝口氏 斎藤正夫
〈小報告〉「五十公野御茶屋」の棟札 藤間登
越後俳諧史抄 ―近世新発田を中心として― 嶋村秀夫
溝口出雲守様弥彦お通り 土田義男
―高橋光則日記による―
越後戊辰戦争 ―新発田藩の動向について― 河村銈一
三面川の筏流し ―朝日村下新保の聞書― 佐久間惇一
八幡の盆踊り 五十嵐 東
(新刊紹介)荻野正博著
『自由な空―大杉栄と明治の新発田―』 高橋礼弥
史料 寛政三年・同四年 御触書・申渡留帳(二)
町奉行 高橋礼弥 翻字
(書評)中野豈任『祝儀・吉書・呪符』
『忘れられた霊場』 大沼淳
〈史跡探訪〉喜多方市史跡等探訪 福岡光二
■ 第18号 平成2年(1990)4月20発行
〔口絵〕・伝 加治要害山麓出土の珠洲焼四耳壺
・同上 常滑焼三筋壺
・香伝寺墓地の近世礫石墨書供養塔婆〔史料一・二〕
『芝田古今詩稿』とその周辺(下) 帆刈喜久男
新発田藩における寺領新田
―五十公野石仏庵石仏新田の分析― 伊藤充
新発田藩と鷹について 佐久間惇一
新発田藩の天保改革 星野尚文
堀部安兵衛武庸覚書(中)
―故郷の人々への書簡― 高橋礼弥
中山安兵衛遺品里帰りの顛末 遠藤利信
堀部家の後裔(二) 五十嵐喜一郎
中米に新天地を求めた小川富一郎 松田時次
大倉喜八郎 ―政商と製糸への道― 河村銈一
大倉喜八郎の記念樹と菩提寺 能仲貫一
鎮守様の鳥居 菊地公治
溝口半左衛門家 斎藤正夫
新発田藩の名主職
―松浦六日町の肥田野家の場合― 藤間登
八幡の灯篭かつぎ 五十嵐東
新発田町の古い電話番号簿 本井晴信
伝 加治要害山麓出土の中世陶器 鶴巻康志
香伝寺墓地の近世礫石墨書供養塔婆について 鈴木秋彦
史料 寛政五年・七年
御触書・申渡書留帳(新発田藩町奉行)高橋礼弥 翻字
(書評)中島欣也『銀河の道―社会主義中尉松下芳男の生涯』
荻野正博
〈史跡探訪〉・松浦地区史跡探訪・加地城址の史跡探訪
・会津若松市史跡探訪
第四回「越後と会津を語る会」参加記 高橋礼弥
〔囲み記事〕
・「北越月令」―新発田分―(七)~(一一) 佐久間惇一
・鷹狩の獲物の拝領について 佐久間惇一
・神指城の築城について (佐久間)=佐久間惇一
(新刊紹介)
・『昔のしばたの暮らし叢書 第二集』(佐久間)=佐久間惇一
・新潟県曹洞宗青年会編『曹洞宗新潟県寺院歴住世代名鑑』
深井一成
・細野明夫著『鶸とり物語―くびき八景―』 鈴木秋彦
■ 第19号 平成3年(1991)4月18日発行
〔口絵〕・縄文時代の炉跡(館ノ内遺跡)
・定点観測(新発田市中央町三 万松堂書店前)
特集 第五回「会津と越後を語る会」
歓迎の挨拶 新発田市長 近寅彦
開催にあたって 新発田郷土研究会副会長 松田時次
記念講演 北辰戊辰戦争に思うこと 作家 中島欣也
研究発表 珠算研究家星伊策と越後
会津史学会 大塚 実
研究発表 地方御用状留記にみる新発田藩御用の
寄人馬について 喜多方古文書研究会 川口芳昭
研究発表 境の神ショーキ様 ―ルーツを
たどった子供たち― 阿賀路の会 佐藤修司
研究発表 鎌倉~戦国期における会津と越後
新潟郷土史研究会 竹田和夫
研究発表 新発田藩にまつわる戊辰霊苑墓碑のなぞ
新潟戊辰の会 小山種三郎
研究発表 北越戊辰戦争とW・ウイリス
新発田郷土研究会 荻野正博
第五回「会津と越後を語る会」開催を終えて 川瀬勝一郎
新発田藩の口留番所 桑原孝
近世前期の江戸送り荷 中山清
十代藩主溝口直諒と藩校教授たち(上) 帆刈喜久男
長堀検校とその妻みねのこと
―新発田が生んだ幕末の総録検校― 長嶺敬子
堀部安兵衛武庸覚書(下)
―故郷の人々への書簡― 高橋礼弥
堀部安兵衛が後事を託した人々 遠藤利信
芝田村の氏神「伊勢堂」について 長谷川惣蔵
泰道泉明と宝筐印塔について 深井一成
道賀新田の肥田野三郎次の家 藤間登
郷土の神社の注連縄について 菊地公治
ショウキ様を訪ねて 五十嵐東
祝い唄「松坂節」考 渋谷善雄
大倉翁碑と佐藤六石碑 斎藤正夫
史料 寛政七年御触書・申渡書留帳
(新発田町奉行)(一) 高橋礼弥 翻字
史跡探訪報告〔新発田市猿橋・佐々木
聖籠町 紫雲寺町〕 福岡光二
〔囲み記事〕
・お代官様のお泊まり(一)・(二)・(三)・(四)
(高橋)=高橋礼弥
(新刊紹介) 佐久間惇一著『新発田地方の民謡集』
■ 第20号 平成4年(1992)4月20日発行
〔口絵〕・明治三〇年当時の清水谷御屋敷絵図
・定点観測(新発田市中央町三 万松堂書店前)
博物館建設のプロセス
國學院大学考古学資料館長 加藤有次
「郷土博物館」(仮称)建設問題への取組み 新発田郷土研究会
佐藤六石翁とその自用印について 岡村浩
奥会津における丸太の流送について(上) 佐久間惇一
沼垂湊・新潟湊訴訟と新発田藩の対応 高橋礼弥
―新発田組庄屋斎藤加兵衛控を中心に―
小泉蒼軒の言語記録 帆刈喜久男
明治期における清水谷御殿の記録 松田時次
東町甚兵衛船朝鮮国へ漂着一件之記録 長谷川惣蔵
明和七年新発田藩廻米船朝鮮国漂着のことなど 鈴木秋彦
中世の一事件による高浜条と島潟周辺 石澤幸市
シベリア出兵反対運動と新発田人 荻野正博
原宏平翁を偲んで 遠藤利信
猪股節斎翁寿碑 藤間登
蓑口サイサイ考 五十嵐東
魚沼の祝儀唄「魚沼松坂」に思う 水落忠夫
高野山にある新発田藩主溝口家の墓塔群 鈴木康
レポート 新発田藩主溝口氏出自をめぐって 遠藤利信
史料 寛政七年御触書・申渡書留帳(二) (新発田藩町奉行)
〔囲み記事〕
・御家督以来御公務御入用調(一)・(二)・(三)
・「藤氏別館(墅)」一束 (一)・(二)・(三)・(四) 遠藤利信
・福島潟でもヒラメが捕れた 鈴木秋彦
(郷土本の紹介)『昔のしばたの暮らし』
叢書 第二・三・四集 福岡光二
史跡見学会報告
〔新発田市旧鴻沼村地区 加治川村 黒川村〕
佐久間惇一先生文部大臣表彰祝賀会報告 鈴木秋彦
第21~30号
■ 第21号 平成5年(1993)4月30日発行
〔口絵〕・福島県耶麻郡西会津町真福寺本堂の奉納絵馬
・定点観測(新発田市中央町三 万松堂書店前)
新発田俳諧史(一) 帆刈喜久男
新発田と周辺の遺跡探訪 小野田十九
「奥会津における丸太の流送について」(下) 佐久間惇一
地名、名称等について(八幡の事例) 五十嵐東
寛政年間次第浜名主役の異動
―月番日記を資料として― 深井一成
不思議降る 天保元年の怪事件 鈴木康
新発田藩における「能」の記録と野村伝之丞 長谷川惣蔵
御城下、東町神明宮に関する記録 長谷川惣蔵
―十代直諒公前期の時代(月番日記)―
日の丸と溝口健齋公 遠藤利信
新発田の中の朝鮮史抄 鈴木秋彦
中条町の移り変わり 柳澤章
しばたところどころ歴史の散歩道 鈴木昭
山口賢俊先生を偲んで 森田国昭
史料 慶応四年辰年九月小戸村戦争覚書 遠藤満
史料 寛政八年・同十一年
御触書・申渡書留帳(町奉行)(一) 高橋礼弥
(史料紹介)新発田藩の朝鮮通信使御馳走役
(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)高橋礼弥
史跡見学会報告 〔中条町〕〔福島県西会津町〕 福岡光二
■ 第22号 平成6年(1994)31月日発行
〔口絵〕・「日本図屏風」(部分)に見える「下井濱」
・定点観測(新発田市中央町三 万松堂書店前)
中条町と会津八一 高沢吉郎
第七代藩主溝口直温(上) 帆刈喜久男
新発田領内元禄寺院書上げの写本について 深井一成
―小田寿吉氏旧蔵本と三扶誠五郎氏石版刷本―
東蒲原にゆかりのある久米三輔医師と父久米幸太郎 徳永次一
新発田台輪の煽りについての覚書 佐久間惇一
紫雲寺潟新田の西縁り飛地の諸問題 宮川四郎兵衛
木蘭の詩の屏風(宝光寺蔵)について 藤間登
角石原の戦いを偲ぶ 遠藤利信
民間信仰と講と板碑 石澤幸市
史料紹介「西洋人の描いた日本地図」記載の
「次第浜」について 鈴木秋彦
続 しばたところどころ歴史の散歩道 鈴木昭
新発田藩之日記に現れる
市嶋次郎八の事績(其の一) 長谷川惣蔵
他国に葬られた小戸の女たち
―金比羅詣りの悲劇― 遠藤満
米軍進駐と新発田(一)
―情報も配給・飛び交う流言―米軍到着前の嵐 井上正一
史料 正徳一組騒動書 高橋礼弥
佐久間惇一氏を悼みて 松田時次
吉川象市を思う 森田国昭
〔囲み記事〕
・七不思議(一)(二) (遠藤)=遠藤利信
・立売町の故事 (高橋)=高橋礼弥
・新発田屋のこと 鈴木秋彦
・川口栄三コレクション郷土玩具の現在 鈴木秋彦
史跡見学報告 〔米沢市〕〔豊栄市〕 福岡光二
■ 第23号平成6年(1994)12月28日発行
〔口絵〕・溝口秀勝判物
・定点観測(新発田市中央町三 万松堂書店前)
岩村金策について 松田時次
通称地名について 高橋善夫
新発田藩之日記に現れる
市嶋次郎八の事績(其の二) 長谷川惣蔵
大杉栄はいかに葬られたか 遠藤利信
小戸の山で銀鑛と白土を発見 遠藤満
続 しばたところどころ歴史の散歩道 鈴木昭
米軍進駐と新発田(二)
―第二の黒船「ジープ」― 井上正一
史料 御触書・申渡書留帳(二) 高橋礼弥
斎藤正夫先生の思い出 鈴木秋彦
史跡等見学報告 〔上越市〕〔紫雲寺町〕 福岡光二
■ 第24号 平成7年(1995)12月28日発行
〔口絵〕・奥州新御領絵図
・定点観測(新発田市中央町三 万松堂書店前)
北蒲を舞台とした漢詩人(一)
―長沢松雨の風流韻事― 岡村浩
両新田のサイサイ踊り 五十嵐東
安政四年、加治川堤、嶋潟切れ之記録
―新発田藩、月番日記― 長谷川惣蔵
新発田様への御用流木と筏乗りの事 遠藤満
近江源氏佐々木一族の興亡(一) 柳沢章
菅谷寺懐古 鈴木昭
野口多内翁の生涯 遠藤利信
米軍進駐と新発田(三)
―有刺鉄線の向こうのアメリカ― 井上正一
史料 寛政十一年六月・十二月御触書・申渡書留帳(三)高橋礼弥
〔囲み記事〕・新発田で印刷の十円札(遠藤) =遠藤利信
史跡見学報告〔鶴岡市〕〔北蒲原郡南部郷町村〕 福岡光二
第25号 平成8年(1996)12月28日発行
〔口絵〕・新潟県有形文化財古文書 正保越後国絵図
・定点観測(新発田市中央町三 万松堂書店前)
北蒲を舞台とした漢詩人(二)
―中央詩壇の重鎮 佐藤六石― 岡村浩
大正期に於ける新発田駅にまつわる話題あれこれ 松田時次
新発田市本間新田開拓史(一) 高橋礼弥
苦労した新田開発 遠藤満
京洛に新発田藩縁りの地を訪ねて 高橋善夫
新発田藩の名主 椎谷良平
新発田藩「御菜園」の記録
―幕末期の月番日記― 長谷川惣蔵
天明元年の加治川、新太田川等出水、
堤切れの記録
―新発田藩の月番日記― 塩原弘
会津・越後往還雑考 宮川四郎兵衛
陸行か、水行か、
―「奥のほそ道」芭蕉の「越後路」― 板倉功
しばた ところどころ 鈴木昭
近江源氏佐々木一族の興亡(二) 柳沢章
米軍進駐と新発田(四)
―チョコレートと民主主義― 井上正一
史料 寛政十二申年 御触書・申渡書留帳(三) 高橋礼弥
交流会、史跡見学報告〔石川県加賀市〕 福岡光二
■ 第26号 平成9年(1997)12月28日発行
〔口絵〕・新発田城第八地点の発掘調査
・定点観測(新発田市中央町三 万松堂書店前)
新発田藩最後の姫君 溝口歌子の生涯(一)
―大名華族の家に生まれて― 藤崎千代子
―ブラジルコロニアの先駆者―岸本昴一の生涯 松田時次
新発田市本間新田開拓史(二) 高橋礼弥
新発田藩の名主(二) 椎谷良平
享保二年新発田藩月番御用留書抜粋記(その一)
―一七一五年五代藩主溝口重元侯の時代― 長谷川惣蔵
幕末前後新発田藩の超倹約令
―新発田藩「御在城御留守日記」― 高橋孝雄
舊新発田藩祖入封三百年祝祭 荻野正博
三平一件ニ附江戸日記 遠藤満
伊能忠敬の新発田領通行とその対応 深井一成
近江源氏佐々木一族の興亡(三) 柳沢章
米軍進駐と新発田(五)―軍用車の群れ― 井上正一
史料 寛政十二申年
御触書・申渡書留帳(二)町奉行 高橋礼弥
第十二回「会津と越後を語る会」参加の記 高橋礼弥
新発田の「狐尾曳ノ城」伝説について 鈴木秋彦
〔囲み記事〕
・大倉喜八郎の豪快なる生涯
・大倉喜八郎と張作霖
・石ころ缶詰事件の真相 (一)(二)
史跡見学報告〔中蒲原郡横越町・新津市〕 福岡光二
■ 第27号 平成11年(1999)3月31日発行
〔口絵〕・丹羽長秀判物
・磨製石斧(新発田市虎丸 坂の沢C遺跡出土)
北蒲を舞台とした漢詩人(三) 岡村浩
新発田藩最後の姫君 溝口歌子の生涯(二)
―伯爵令嬢から職業婦人へ― 藤崎千代子
溝口軌景幽軒(上) 帆刈喜久男
剣聖・今井常固先生の足跡と「発誠館道場」 佐藤泰彦
―生誕一五〇年によせて―
新発田城下町物語(一) 高橋礼弥
蒲原宝暦騒動と新発田藩の農政 椎谷良平
享保二年・新発田藩月番御用留書抜粋記(其の二)
―一七一五年五代藩主溝口重元侯の時代― 長谷川惣蔵
小戸村庄屋役引き継ぎ資料 遠藤満
本家市島家と福島潟(上) 松田時次
史料 享和元年一月から二年二月まで
申渡留帳 町奉行 高橋礼弥
史跡見学報告 〔新潟市〕 福岡光二
■ 第28号 平成12年(2000)3月31日発行
〔口絵〕・寶暦九年銘瓦の出土
北蒲を舞台とした漢詩人(四)・補遺 岡村浩
新発田藩最後の姫君 溝口歌子の生涯(三)
―薬学を学び自立へ― 藤崎千代子
本家市島家と福島潟(下) 松田時次
溝口藩「直心影流」剣術師範
窪田鐐三郎傳習先生の事績 佐藤泰彦
享保二年、新発田藩月番御用留書抜粋記(其の三)
―一七一七年五代藩主溝口重元侯の時代― 長谷川惣蔵
新発田城下町物語(二) 高橋礼弥
新井田の全昌寺 遠藤満
文久年間の真野原郷開発について
―誰が阿房堀と呼んだのか― 深井一成
米軍進駐と新発田(六)―星条旗とラッパ― 井上正一
「特集」 第十四回 会津と越後を語る会
開会にあたって 新発田郷土誌研究会会長 松田時次
歓迎のごあいさつ 新発田市長 片山吉忠
開催にあたって 新発田市教育長 臼井茂夫
研究発表
会津の軽井沢銀山 塩川振興会 佐藤一男
傑堂能勝禅師と会津天寧寺
会津坂下町文化財調査審議会委員 高橋一郎
久米三輔医師と東蒲原郡阿賀路の会 徳永次一
―仇討で有名な久米幸太郎の子―
明治戊辰戦争と新発田藩家老窪田平兵衛
新発田郷土研究会 河村銈一
記念講演 「会津・越後文人往来」
日本近世文学会会員・俳文学会員 帆刈喜久男
第十四回「会津と越後を語る会」を終えて 川瀬勝一郎
史跡探訪報告〔岩船郡朝日村 奥三面遺跡〕 福岡光二
史料 享和元酉年・二戌年 申渡留書 町奉行
■ 第29号 平成13年(2001)3月31日発行
〔口絵〕・すり鉢を伏せた墓(松橋遺跡出土)
稲葉黙齋と新発田藩学 帆刈喜久男
新発田藩最後の姫君 溝口歌子の生涯(四) 藤崎千代子
―薬学界、そして癌学会へ―
新潟県人苦闘の記録(上)
―ペルー移民のパイオニヤ― 松田時次
新発田城下町物語(三) 高橋礼弥
直心影流・発誠館道場三代目館長 中村新蔵先生の
プロフィール ―その後の発誠館― 佐藤泰彦
新発田藩における伊勢参宮
―聖籠地域を中心として― 椎谷良平
新潟県の大正デモクラシー(上)
―普選運動を中心に― 荻野正博
再び=「おくの細道」越後路について 板倉功
米軍進駐と新発田(七)
―世紀の大実験 日本軍総復員― 井上正一
史跡見学報告〔南蒲原郡下田村・中蒲原郡村松町〕福岡光二
■ 第30号 平成14年(2002)2月28日発行
〔口絵〕・要害山の麓で発見された壺
・石の卒塔婆(新発田市上三光 宝積寺)
新潟県の裸押合い祭り 佐藤和彦
新発田藩最後の姫君 溝口歌子の生涯(五)
―情報管理の独立独行の先駆者― 藤崎千代子
新発田俳諧史(二)
―信杖汻虹とその時代(上)― 帆刈喜久男
新発田城下町物語(四) 高橋礼弥
戊辰戦争時の『軍事日記』について 鈴木康
戦争の狭間に生きた人びと
―三扶尚三のことなど― 佐藤博信
新潟県人苦闘の記録(下)
―ペルー移民のパイオニヤ― 松田時次
シシトリの遭難 遠藤満
柿本清吉先生の足跡
―名声を天下に馳せた江戸詰剣士― 佐藤泰彦
新潟県の大正デモクラシー(中)
―普選運動を中心に― 荻野正博
米軍進駐と新発田(八)
―複数の顔を持つアメリカ― 井上正一
史跡見学報告〔長岡市〕 福岡光二
第31~40号
■ 第31号 平成15年(2003)3月31日発行
〔口絵〕・百三十年ぶりに姿を現した新発田城辰巳櫓
新発田城特集
城下町新発田の成立と近代化の研究 渡辺幸二郎
新発田城の三階櫓・辰巳櫓と日本の城 松田時次
新発田城本丸内の櫓・石垣の建設と修復の覚書 高橋礼弥
新発田俳諧史(三)
―信杖坊汻虹とその時代(中)― 帆刈喜久男
伊藤精司先生の事跡
―発誠館が生んだ陸軍の名剣士― 佐藤泰彦
横山大観来芝並びに拾円紙幣印刷について 柳沢章
新潟県の大正デモクラシー(下)
―普選運動を中心に― 荻野正博
小和田恆先生ご生誕の家
―幻影と実態を追う― 井上正一
河村銈一先生を悼む 平山靖夫
史跡見学報告
〔西蒲原郡巻町・分水町・寺泊町・出雲崎町〕福岡光二
■ 第32号 平成16年(2004)3月31日発行
〔口絵〕・新発田相鎮守諏訪神社 再建上棟式(拝殿)のスナップ
撮影・解説 鈴木秋彦
台輪人形の謎 高橋善夫
藤川善海先生の事略とゆかりの人々
―発誠館今井道場・今井常固先生の 佐藤泰彦
門人として花開いた最後の剣士―
大杉栄と田口運蔵(上)
「殿様俳人溝口梅郊」補遺 帆刈喜久男
阿賀野川の変遷 高橋礼弥
『ふるさと新発田』の名称 若林 稔
「目」にかかわる生活文化覚え書き 鈴木秋彦
米軍進駐と新発田(九)―勝者と敗者― 井上正一
新発田青年会について
―『新発田青年会誌』の紹介― 荻野正博
史跡見学報告〔田上町・加茂市・三条市〕 福岡光二
■ 第33号 平成17年(2005)3月31日発行
〔口絵〕・箱館跡の発掘調査
新発田の和歌の伝統と原宏平 帆刈喜久男
上杉景勝過所をめぐって 阿部洋輔
剣士・佐藤毅先生の軌跡 佐藤泰彦
―範士九段まで昇りつめた剣道界の重鎮―
大杉栄と田口運蔵(下)
―その「自由」と「反逆」の原点― 荻野正博
新井田あれこれ 遠藤満
しばたことば「…ネッシ(ス)」考 板倉功
溝口伊織家文書にみる鮑の信仰 鈴木秋彦
新発田市観光ガイドボランティア協会の
活動について(報告) 若林稔
史跡見学報告〔新発田城〕 福岡光二
■ 第34号 平成18年(2006)3月31日発行
〔口絵〕・城中請取書(東京鎮台第一分営が新発田城接収の史料)
『しばた台輪』はなぜ壊れないのか
―柱と前輪の強度検証結果― 渡辺幸二郎
発誠館・今井道場の復元模型について 佐藤泰彦
米倉(新発田)斎藤家、並びに肥田野家の系図 板倉功
中学新発田校覚え書 荻野正博
六十年回顧の一片 高橋孝雄
新発田藩の庭園と御露地方の資料 鈴木秋彦
高橋礼弥編著『新発田藩年代記』について 阿部洋輔
『新発田案内』(大正二年)について 荻野正博
野口孝司氏の死を悼む 松田時次
〔囲み記事〕・聖籠のオオタカ
(新刊紹介)
・茂沢祐作著『ある歩兵の日露戦争従軍記』
・板倉 功著『桜田門外ノ変 関鉄之介伝』
・板倉 功編著・肥田野保之監修『江戸へ参り申し候』
新発田郷土誌ニュース史跡見学報告 〔旧豊浦町地区〕福岡光二
■ 第35号 平成19年(2007)3月31日発行
〔口絵〕・加治天王前遺跡の発掘調査
良寛・由之兄弟と井上桐麿との交流 冨沢信明
佐藤尚志復斎 帆刈喜久男
剣術世話役・溝口周太―その功績と評価― 佐藤泰彦
登坂北嶺「遊京日記」(一) 荻野正博
「大峰山」のヤマザクラは何処から
―「熊野信仰」と「下越」― 板倉功
新発田藩家臣団の通婚行動 久住祐一郎
「江戸時代の新発田を読む」会を終って 阿部洋輔
史跡見学報告〔旧紫雲寺町地区〕 福岡光二
松田時次先生を悼む 川瀬勝一郎
(参考資料)新発田市における指定文化財一覧表
(新刊紹介)
・高橋やすお著『新発田俳句叢書一新発田俳壇小史』 鈴木秋彦
・新発田古文書解読会編
『二〇周年記念誌歩み』 鈴木秋彦
郷土誌ニュース 板倉功
■ 第36号 平成20年(2008)3月20日発行
〔口絵〕・新発田城跡第一九地点の発掘調査
建築としてのカトリック新発田教会 渡辺幸二郎
新発田が発祥と思われるもの
―当地域特異の風習について― 高橋善夫
登坂北嶺「遊京日記」(二) 荻野正博
二つの「慶長三年 殿様御入国御供記」を検証する 鈴木博
新潟・沼垂の湊訴訟から見る江戸留守居役 久住祐一郎
岩船柵、後の越後城は、加治川水系か胎内川水系にあり 木村恬文
良寛の出奔から参禅そして出家への道 冨沢信明
小報告 大杉栄の新発田来住と母豊(トヨ)の死 荻野正博
堀部安兵衛弁護 遠藤利信
史跡見学報告 〔旧加治川村地区〕 福岡光二
高橋禮彌先生を悼む 鈴木秋彦
―高橋禮彌先生著述目録(稿)・高橋禮彌先生略年譜―
(新刊紹介)・佐藤泰彦著『城下町新発田の剣道史』上・下巻(荻野)=荻野正博
・人間国宝 天田昭次著『鉄と日本刀』 遠藤利信
■ 第37号 平成21年(2009)3月20日発行
〔口絵〕・北嶺 登坂良平展
高野山に供養された新発田の人びと 阿部洋輔
子規による和歌革新の源泉は良寛にあり 冨澤信明
士族授産のため開拓に挑んだ溝口内匠(甚太郎) 佐藤恒男
畠山重章氏(宮司就任前畠山弄月の筆名にて与茂七実傳の著者)
記述の中の嶋講話草稿について 高橋善夫
登坂北嶺「遊京日記」(三) 荻野正博
「新発田藩主寄進の石燈籠」を訪ねる 鈴木博
次第浜の「山王さん」 星野建士
戊辰中間決算 小泉秀也
史料紹介『土芥寇讎記』所収
「溝口宣広」記事 荻野正博
わが家の伝承―和算家黒岩吉治のことなど― 黒岩 高
火事帽子 相澤和夫
北嶺 登坂良平展出品目録 荻野正博
〔囲み記事〕・赤橋の湯 相澤和夫
・木砲 相澤和夫
・池内 紀『書棚のショートストップ』より (荻野)=荻野正博
・泉町の額面纏の書家 小竹老人(一)(二) 鈴木秋彦
・登坂良平「日記」より(一)(二) 荻野正博
史跡見学報告
〔新発田市池之端・八幡・天の原・赤谷・山内〕 皆木邦夫
■ 第38号 平成22年(2010)3月20日発行
〔口絵〕・新発田藩初代藩主・溝口秀勝公四百回忌
明治三十四年帰郷後の登坂北嶺 荻野正博
東華堆朱 大宮司久明
一本木原御林再考 富井秀正
八幡近郊の川原石について
―米蔵川、佐々木川、新発田川― 五十嵐東
諏訪神社と町方の関わりに付いて 高橋善夫
明治二年丸山直方医学修行のため
京都へ遊学した時の文書 樋口義健
宝光寺の大乗妙典一千部塔について 深井一成
―大而宗龍の事跡に関連して―
新発田藩の鉄砲 小泉秀也
庄内藩にみる士族授産・興産事業 佐藤恒男
~国指定史跡「松ヶ岡開墾場」を訪ねる~
武道の名人達人の思い出 黒岩高
「新発田藩主寄進の石燈籠」を訪ねる(二)
~境の明神に七代藩主・直温侯が寄進の石灯籠~ 鈴木博
随想 寺田ヒロオ再読~作品における光と影~ 佐藤栄征
戊辰戦争従事の褒美の茶碗 佐藤十三雄
蔵光区有文書と越佐歴史資料調査会 相澤和夫
〔囲み記事〕
・新発田の名物 (荻野)=荻野正博
・男尊女卑 相澤和夫 ・竹ヶ花 相澤和夫
・「高橋禮彌基金」による古文書購入報告 鈴木秋彦
・急々軍隊取立仕法 相澤和夫
・上杉景勝の上洛と溝口家 阿部洋輔
(新刊紹介)・新潟の地震編集委員会編
『新潟の地震 増補版』 青木泰俊
史跡見学報告〔弥彦村・新潟市西蒲区〕・〔福島県磐梯町〕 皆木邦夫
■ 第39号 平成23年(2011)3月20日発行
〔口絵〕・佐藤哲三『ダリア』『労働者』『農婦』
『郵便脚夫宮下君』 『越後の秋』
蒲原に生きた画家・佐藤哲三小伝 小見秀男
海軍少佐溝口武五郎と金州丸遭難事件 相澤和夫
最後の旗本・溝口勝如 小泉秀也
大倉喜八郎が踏襲した学問を検証する 大沼長栄
大倉喜八郎「石の缶詰事件」を辿る 肥田野由美
内蔵助と安兵衛さん 木村恬文
不発爆弾発見の報道に思う 黒岩 高
明治二年丸山直方医学修行のため京都へ
遊学したときの文書 続編 樋口義健
中村の若宮八幡神社改修 平野利夫
寺田ヒロオさんとの出会い 一番弟子の自認 渡邊貫二
宝光寺御墓所掃除にかかわる一資料 荻野正博
駒込・吉祥寺の溝口家墓域の現状と課題
―藩主と奥方・御実母たちの墓塔― 佐藤泰彦
歴史フォーラム ~江戸時代に学ぶ「新発田藩と江戸幕府」~
〔囲み記事〕
・最後の巡見使 一九
・水原代官所の金納年貢米価 相澤和夫
・庄内の棟梁 高橋兼吉 佐藤恒男
・江戸時代の土地制度 相澤和夫
史跡見学会報告(聖籠町地域) 藤間殖
渡辺幸二郎氏を悼む 荻野正博
■ 第40号 平成24年(2012)3月20日発行
〔口絵〕・諏訪神社 大西孫右衛門門弟火術訓練掲額
・市島邸に設置された市島謙吉像
・襲撃事件当日の日誌
・新発田警察署からの被害者召喚状
郷土出身の草莽の志士たち
―居之隊員の心の支柱若月元輔と二人のリーダ
ー松田秀次郎と二階堂保則― 佐藤恒男
諏訪神社 大西孫右衛門門弟火術訓練掲額 荻野正博
青年政治家 市島謙吉の活躍 長嶋晃一
新発田出身「近藤谷一郎」巡査の
殉職について(ご紹介) 佐藤進
新発田藩と公家 小泉秀也
昔々、米占領軍が新発田にやって来た 鈴木昭
「伝習録」を座右の書に
―大倉喜八郎の事業経営― 大沼長栄
十代直諒侯医師論 高橋善夫
駒込・吉祥寺「溝口家代々之墓」のある墓域と
「溝口家累代之墓」(分家)の調査 佐藤泰彦
武家年中行事の変容
―新発田藩具足開きを例として―(一) 鈴木秋彦
生家に残る「家系図」に見る三題 奥村祥吉
電灯話つれづれ 黒岩高
北区内島見・近藤家文書について その一
―当道座文書について― 広瀬秀
溝口直諒侯お茶会のお菓子 近藤睦
坂上達日記 樋口義健
「新発田藩月番日誌」の翻字による
賭博・樗蒲の処罰 林チヨエ
「故若林稔氏蔵書展示」を顧みて 鈴木昭
報告 新発田ロータリー例会卓話 荻野正博
〔囲み記事〕
・新発田高女の体格 肥田野由美
・大倉製糸須坂工場のステンドグラス 鈴木博
・怪文「隣触」 相澤和夫
・有栖川宮熾仁親王殿下の来芝 肥田野由美
・天王の市島邸 相澤和夫
・大隈重信 二十時間の新発田訪問 長嶋晃一
・~ロマン~ 都岐沙羅柵は何処に 佐藤英行
史跡見学会報告 〔新潟市〕 皆木邦夫
第41~50号
■ 第41号 平成25年(2013)3月20日発行
〔口絵〕・古四王、その神格と分布を探る
・淡島大権現堂(上鉄砲町・敬学院境内)
古四王、その神格と分地を探る 佐藤榮征
新発田藩定雇、大工、梅之丞の家計の研究
―「入れ歯師」に変身した梅之丞親子について―佐藤泰彦
常昭記録
―幕末における新発田藩下級武士の生涯― 荻野正博
新発田藩学より見た戊辰戦争
―家老溝口半兵衛手記に残る新発田藩の姿勢―大沼長栄
探訪 中世山城跡(一) 伊藤久司
坂上達日記(二) 樋口義健
武家年中行事の変容
―新発田藩「具足開き」を例として―(二)―鈴木秋彦
芸能からみた元禄赤穂事件と堀部安兵衛像 阿部聡
豊田神社拝殿の「新発田藩領図額
〈含・奥州八島田〉」の奉納経緯 鈴木博
溝口直温画「青不動」著賛の黒太淳について 深井一成
魯迅と蕗谷虹児の接点 木村恬文
北区内島見・近藤家文書についてその二
当道座文書について(続) 広瀬秀
新発田藩主の佩刀 小泉秀也
郷土出身の草莽の志士たち 居之隊員の心の
支柱若月元輔と二人のリーダー
松田秀次郎と二階堂保則(下) 佐藤恒男
(資料)故郷のお山 歴史のお山
―七葉小学校生徒登山の手引き― 黒岩高
(史料)武庸会記録 冨澤信明
川瀬勝一郎先生を悼む 平山靖夫
〔囲み記事〕
・乙川優三郎(平成十四年直木賞受賞者)
『蔓の端々』(講談社)より 引用者 荻野正博
・庄内藩中老 石原倉右衛門の死 佐藤英行
(新刊紹介)
・『教育村川東―本間百在門と村人の軌跡―』 高山昭憲
・新発田大火(昭和十年九月十三日)直前の
西ヶ輪商店街と下町神明神社界隈商店街の街並み 鈴木博
史跡見学会報告(川東・菅谷地区) 藤間殖
『新発田郷土誌』総目次 第一号~第四十号 長嶋晃一
■ 第42号 平成26年(2014)3月20日発行
〔口絵〕・新江用水
・明治天皇 北陸御巡幸 五十公野杉畷(すぎなわて)
堀部安兵衛は出府当初芝切通し辺に
移住して手習師匠をしていた 冨澤信明
北の海に活路を求めた人びと 佐藤榮征
新発田藩の人口 小泉秀也
宮下辰次郎の日記 樋口義健
新発田藩政時代の第土木工事(新江用水) 渡辺孝明
町村段階における北蒲原尋常中学校設立の事情
―蓮野村村会議事録から知られること― 荻野正博
眼科刀工・異色の才人―梅田信義氏について― 佐藤泰彦
探訪 中世山城跡(二)―赤谷地区の山城― 伊藤久司
戦後の新発田における看護師の返還 小野澤隆
『天子養老典祝文』について 黒岩高
北区内島見・近藤家文書について
その三 近藤文泰と大森寿庵(一) 広瀬秀
明治天皇北陸・東海御巡幸と新発田 大沼長栄
武家年中行事の変容 鈴木秋彦
―新発田藩「具足開き」を例として―(三)
祖父柳川勝を偲ぶ―記録をたどって―(一) 柳川勝郎
(新刊紹介)『武庸会百周年記念誌』
発行 武庸会百周年祭実行委員会
・宮野泰著「タムガ村600日キルギス抑留の記録」 鈴木秋彦
・「新劇の父・劇団俳優座育ての親」青山杉作 星野守雄
東京都内研修報告 長嶋晃一
史跡見学会報告(新潟市秋葉区・阿賀野市保田地区)藤間殖
石﨑政弘先生を悼む 鈴木秋彦
平成二十六年度「会津と越後を語る会・新発田大会」の
概要について 新発田大会実行委員長 皆木邦夫
■ 第43号 平成27年(2015)3月31日発行
〔口絵〕・新発見の堀部安兵衛肖像(野村芳光画)
・石塚三郎の生家(石塚三郎旧蔵ガラス乾板)
吉田東伍記念博物館蔵
幕末の新発田藩と海防問題
―海防問題―軍備増強・洋式訓練 荻野正博
称賛なり 新発田藩 木村恬文
管見 阿賀北方言の歴史性 佐藤榮征
梅田信義さんを思う 黒岩高
新発田藩のお手伝い 小泉秀也
吉良邸討入りは何故大成功したのか
―吉良屋敷替えの謎を解く― 冨澤信明
祖父柳川勝を偲ぶ―記録をたどって―(二) 柳川勝
北区内島見・近藤家文書について 広瀬秀
その四 近藤文泰と大森壽庵(二)
武家年中行事の変容
―新発田藩「具足開き」を例として― 鈴木秋彦
『肥田野家』先人達の生きし日々の証を擦って 肥田野順一
大木幹雄先生を悼む 鈴木秋彦
第二十八回 会津と越後を語る会 新発田大会
新発田郷土研究会会長 佐藤泰彦
吉田松陰・冬の諏訪峠越え
会津民俗研究会会長 滝沢洋之
会・越境界にみる戦国の終焉
新発田郷土研究会会員 阿部洋輔
第二十八回「会津と越後を語る会・新発田大会」
を主催して 実行委員長 皆木邦夫
〔囲み記事〕
・「演劇界の巨匠」青山杉作の顕彰碑 星野守雄
■ 第44号 平成28年(2016)3月31日発行
〔口絵〕・大正元年(一九一二)夏 明治天皇崩御追悼剣道大会(於・今井道場)
・播磨国赤穂五万石城主 浅野内匠頭長矩 花岳寺蔵
發誠館・今井道場の集合写真の分析と
武内重六郎の功績について 佐藤泰彦
新発田藩直心影流剣術師範 酒井一也
嶋村外也正武について~「當流愚考」をめぐって
華鮮院と誠心院 ―直溥候の書状より― 前田恵子
新発田藩の献上品 小泉秀也
読書ノート 太平記に加治氏を読む 佐藤榮征
改易された浅野家の赤穂五万石は
何処へ消えたのか 冨澤信明
町村合併の記録 柳川勝郎
祖父柳川勝を偲ぶ―記録をたどって―(三)
崩落大岩石を追う 伊藤久司
―大岩石陰遺跡の崩落岩石群―
赤谷城攻防戦と其の周辺 渡邊大智
滝谷『阿部家文書』 佐藤英行
「越佐歴史資料調査会』に整理が終了する
細野一二先生を悼む 鈴木秋彦
〔囲み記事〕
・歴史用語一口辞典「仙台藩歴史用語辞典」
史跡見学会報告(長岡市 中之島地区) 藤間殖
歴史資料館など建設にむけての
請願・陳情・要望の記録 新発田郷土研究会
■ 第45号 平成29年(2017)3月31日発行
〔口絵〕・林 晴春「武者絵」
・「堀部(中山)安兵衛武庸」の実姉きん所持の短刀(懐刀)
「新発田美術史論考」(一) 臼井茂夫
堀部安兵衛の実子安之助の行方について 冨澤信明
越後に二天一流をもたらした丹羽五兵衛信英と
その薫陶を受けた代々の門弟達が残した史料について 佐藤泰彦
石塔に見る霊場信仰と遠隔地巡礼 佐藤榮征
―新発田地域における近代初頭の事例―
新発田市加治川地区の湯殿山塔 鈴木秋彦
新発田藩と老中 小泉秀也
史料紹介
・「御定書惣目録」について(一) 広瀬 秀
藩公敬慕の文書 新発田藩 柳川勝郎
祖父柳川勝を偲ぶ―記録をたどって―(四)
加治城の隠れた城道
―城館跡比定地の裏山を歩く(一)― 伊藤久司
「新潟・山形・福島の三県に跨る飯豊山信仰の歴史」
福島県民俗学会副会長 小澤弘道
白鷹紀行・小四王原神社と五十公野氏 佐藤榮征
史跡見学会報告
(新潟市江南区沢海地区・秋葉区草水地区)藤間殖
■ 第46号 平成30年(2018)3月31日発行
〔口絵〕・春叢《石楠花咲く》屏風六曲
大正四年第九回文選入選
藩政期・在村鉄砲の規制について 佐藤榮征
堀部安兵衛の実子安之助は熊本藩細川家に三〇〇石で
召し抱えられた堀部中忠兵衛に他ならない 冨澤信明
越後國「蒲原」と「神原」 関川義藏
重元公の正室 小泉秀也
「新発田日本画の逸材」明治~昭和 臼井茂夫
古代下越の役所・郡衙を考える 木村恬文
剣豪今井常固先生を中心とした今井家の系譜 佐藤泰彦
史料紹介・「御定書惣目録」について(二)
―「御定書目録」の検討と新発田藩・新津(安永律)― 広瀬秀
加治城の隠れた城道
―城館跡比定地の裏山を歩く(二)― 伊藤久司
史料紹介・「宝持院所蔵・直温の黄帝図」 佐藤榮征
「新発田市立博物館設立プロジェクトチーム」の立ち上げ
委員長 板倉敏郎
「蔵春閣」が新発田に移築 星野守雄
史跡見学会報告(関川村地内各地) 藤間殖
■ 第47 平成31年(2019)3月31日発行
〔口絵〕・柴田勝家書状(溝口秀雅氏所蔵)
・木戸金左衛門尉福状(溝口秀雅氏所蔵)
溝口家所伝の柴田勝家書状について
―本能寺の変をめぐる― 阿部洋輔
「新発田洋画界の聡明期(その一)」 臼井茂夫
(山本芳翠の『裸婦』をめぐって)
直温公の恋人 小泉秀也
『城下町新発田の剣道史』刊行の意義 佐藤泰彦
戊辰戦争、明治維新一五〇周年考 広井忠男
大目付溝口摂津神は吉良邸討入りを 冨澤信明
成功させた屋敷替えの謀略の黒幕である
「配給ニ関スル書類綴」にみる戦中の暮らし 皆木邦夫
読書ノート・吾妻鏡
鎌倉武士の生きざま―盛綱の子孫の場合 佐藤榮征
古地図の制作意図 関川義藏
新津桂家六代目・東吾誉正と「ほの」との一件 広瀬秀
「新発田ミュージアム設立推進市民会議」の
設立と活動の報告 事務局長 板倉敏郎
史跡見学会報告(新潟市内の歴史) 遠藤木綿子
■ 第48号 令和2年(2020)3月31日発行
〔口絵〕・新発田市宝塔山城跡(願文山)
新発田市金山(伝・円通山観音寺採集遺物)
・史跡見学会報告(福島市・二本松市)
新発田藩分領(福島県)歴史民俗紀行、それらの随想 広井忠男
「新発田洋画界の聡明期(その二)」 臼井茂夫
新発田市宝塔山城跡採集の中世陶器について 小林弘
新發田町三之町保管文書 皆木邦夫
消えゆく葬送の民俗(新発田・胎内地域) 佐藤榮征
本能寺の変・未来永劫の真実 四国征伐の怨恨が
動機であって野望説も黒幕説も成立しない 冨澤信明
堀部家の晩餐 小泉秀也
北越戊辰戦争・溝口半左衛門 木村恬文
直信侯が隠居後又嫡子に復帰した訳 前田恵子
荻野正博先生を悼む ―荻野正博先生
著述目録(稿)荻野正博先生略年譜― 鈴木秋彦
郷土史家・飯田素州先生を偲ぶ 佐藤泰彦
「新発田ミュージアム設立推進市民会議」の活動報告
事務局長 板倉敏郎
〔囲み記事〕
・良寛が訪れた米倉齋藤家と良寛顕彰碑 星野守雄
史跡見学会報告(福島市・二本松市) 遠藤木綿子
■ 第49号 令和3年(2021)3月31日発行
〔口絵〕・昭和初期 新発田洋画界の隆盛期を迎え
・新発田市小戸城跡発見の宗教関連遺物
「新発田洋画界の隆盛期(その一)」 臼井茂夫
『大正デモクラシイと井伊誠一』
―東京と神田時代を中心に― 神田健次
新発田市小戸城跡発見の
宗教関連遺物とその背景― 小林弘
『戦費調達』を支えたもの
新発田町三之町保管文書にみる 皆木邦夫
戦中の暮らし(その三)
金石文「紫雲寺潟願祖略記」を読む 佐藤榮征
―弥勒菩薩の台座に刻まれた史実―
新発田郷土研究会の先達、故野口孝司の
岳父・眼科医師・坂上達先生の事ども 佐藤泰彦
板山集落、秋切り山の山割(分け)と競り 佐藤十三雄
海軍大佐 相馬正平の戦い 小泉秀也
北蒲における地主と小作(一)
~それでも地主が悪いのか~ 山浦健夫
「新発田ミュージアム設立推進市民会議」の
活動報告 事務局長 板倉敏郎
■ 第50号 令和4年(2022)3月31日発行
〔口絵〕・徳川家綱領地朱印状(新発田藩江戸上屋敷文書)
・徳川家茂領地朱印状(新発田藩江戸上屋敷文書)
大倉喜八郎功績の原点
―欧米商業視察と台湾― 大沼長栄
75年前の『蔓延防止』
「町内常會ニ関スル綴」にみる戦後の暮らし(1) 皆木邦夫
「新発田洋画界の隆盛期(その二)」 臼井茂夫
溝口氏受領の領地朱印状について 阿部洋輔
新潟県北部の越後城氏と新発田について 小林 弘
加地氏七代、時秀―波乱の生涯
―元亨から建武~延文まで― 佐藤榮征
寛政元年の二万石高替えについて 佐藤賢次
北蒲における地主と小作2
~それでも地主が悪いのか~ 山浦健夫
「海軍大佐 相馬正平の戦い」続編 小泉秀也
熊倉弘基先生を悼む 鈴木秋彦
平山靖夫先生を悼む 鈴木秋彦
大沼淳先生を悼む 鈴木秋彦
井上正一先生を悼む 鈴木秋彦
黒岩高先生を悼む 鈴木秋彦
近藤睦先生を悼む 鈴木秋彦
新発田郷土研究会のホームページの開設 里村修平
第51号~53号
■ 第51号 創立50周年記念特集号 令和5年(2023)3月31日発行
会員の参加・参画で 会長 皆木邦夫
創立五十周年に寄せて 新発田市長 二階堂 馨
創立50周年おめでとうございます 新発田市教育委員会 教育長 工藤ひとし
[記念講演〕 新発田藩の藩風と新潟県の県民性 伊藤充 新潟青陵大学特任教授
新発田郷土研究会と新発田市立図書館の思い出 副会長 大沼長栄
創立50周年に寄せて 副会長 石川富夫
思い出「新発田郷土研究会」と私 そして「しばたミュージアム」へ 顧問 佐藤泰彦
新発田城復元余話 会員 臼井茂夫
地の利は人の和に如かず 会員 佐藤榮征
新発田郷土研究会の運営に関わって 理事 鈴木秋彦
羽黒山伏の修行に参加して思うこと 理事 加藤博
新発田郷土研究会と私 総務部長 中村明
事業部の活動を振り返って 事業部長 遠藤木綿子
地域の歴史を学ぶ 編集部長 星野守雄
新発田郷土研究会 創立50周年記念事業事績
「会津と越後」・ 「越後と会津」 を語る会の設立と経緯、終了について
新発田郷土研究会50年の歩み 一略年表一
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
地名 「新発田」 〜新発田の成立を探る~ 関川義藏
「秀勝公の働き」 小泉 秀也
山神社と祭神を巡って ―その由来と分布一 佐藤榮征
新発田市板山産黒曜石の先史時代の流通 小林 弘
徳川将軍家一門三十四家六百名の新発明鳥瞰系図 冨澤信明
一新発田溝口家と徳川将軍家一門との姻戚関係一
令和4年度 史跡見学会報告 安達悦司
■ 第52号 令和6年(2024)3月31日発行
石川啄木を世に出した宮崎雨(1) 阿部聡
墾田地名と新田地名(地名の史実) 関川義藏
連合軍の進駐を迎える新発田町民の心得 皆木邦夫
「町内常會に関する綴」にみる戦後の暮らし
イザベラ・バードの阿賀北の旅 佐 藤 茂
坂井川左岸の谷口集落を歩く 佐藤榮 征
―地形、歴史、伝承一
<新発田市松岡>縄文・中世から近代の遺物 小林弘 、湯浅英 仁
歩兵十六連隊を救った駆逐艦 小泉秀也
板山集落、橇で勇壮な木乗り 佐藤十三雄
日本の近代洋風建築の系譜 板倉敏郎
一新発田旧憲兵隊庁舎を考える一
長谷川惣藏先生を悼む 鈴木秋彦
帆刈喜久男先生を悼む 鈴木秋彦
令和五年度史跡見学会報告 遠藤木綿子
■ 第53号 令和7年(2025)3月31日発行
里村英棟と和歌 中澤伸弘
一徳川後期新発田周縁の和歌事情一
石川啄木を世に出した宮崎郁雨(2) 阿部聡
中世池之端氏と中世遺物について 小林弘
新発田における「非軍事化」 皆木邦夫
「町内常會に関する綴」にみる戦後の暮らし(3)
藍染めの軌跡一新発田の昔と今一 佐藤榮征
「直溥公の子女」 小泉秀也
なぜ新発田藩は十万石になったか? 前田恵子
一新発田藩十万石高直りまでの経緯一
明治初期の新発田点描 佐藤 茂
北蒲原の地主と小作3 山浦健夫
〜そんなに地主が悪いのか〜
魅力満載で郷土に元気を吹き込む博物館を 板倉 敏郎
帆刈喜久男先生を悼む(二) 鈴木 秋彦
一帆刈喜久男先生著述目録(稿)一
佐藤榮征先生を悼む 鈴木秋彦
令和6年度 史跡見学会報告 遠藤木綿子